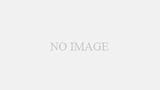指宿竹元病院 高桑 由美子
皆さんは「長谷川式スケール」をご存じでしょうか?
認知症かどうかの診断の物差しになる検査で、日本中で広く使われています。「今日は何年の何月何日ですか?」「100から順に7を引いてください。」などの検査です。その開発者であり、半世紀以上も認知症の医療や介護にかかわり続けてきた医師の長谷川和夫氏が2017年の88歳の時、自身が認知症であると公表しています。当事者となった長谷川氏はその著書の中で、認知症の人はもどかしい思いを抱えて毎日を生きているから認知症への接し方を皆さんに知ってもらいたいと述べています。
認知症の最大の危険因子は加齢です。「人生百年時代」といわれる日本では、誰もが認知症になる可能性があります。厚生労働省によると、団塊の世代が全員75歳になる2025年には5人に1人が認知症になると推計されています。認知症は決して人ごとではないのです。
認知症は恐ろしい病気だと思われがちですが、その本質は暮らしの障害です。それまで当たり前にできていたことがうまく行えなくなる。「普通の暮らし」ができなくなっているのが特徴です。本人はもちろんのこと家族も困惑します。でも、周囲の接し方次第で認知症の人にとっての生きやすさは、かなり違ってきます。
生活のヒントをいくつか紹介します。
- 生活環境をシンプルにする。トイレや寝る場所の位置などを覚えやすく見えやすく動きやすくする
- 接する人は同時に多くのことを言わず、一つずつ分かりやすく目線の高さを同じにして話す
- 何か役割を担っていただく。得意分野ならなおさら引き受けてもらいやすい。そして感謝し、褒める
- 「笑い」も忘れない
そして、何よりも重要なのは、⑤一人の人間としての尊厳を守ることです。認知症になると、周囲はこれまでと違った人に接するかのように、叱ったり子ども扱いしたりしがちです。しかし、本人にしたら自分は別に変わってないし、自分が住んでいる世界は、昔も今も連続している。途端に人格が失われたように扱われるのは、傷つくし不当なことです。
認知症の人も自分と同じ一人の人間であり、この世にただ一人の唯一無二で尊い存在です。
このコロナ禍で、人との関わりが制限される中、多くの高齢者が孤独になりがちです。ただでさえ不安を抱えやすい認知症の人はなおさらです。周囲の人々が正しい知識を持ち、「大丈夫だよ。」と言える地域にしていきたいものです。
参考文献:長谷川和夫著 「ボクはやっと認知症のことがわかった」